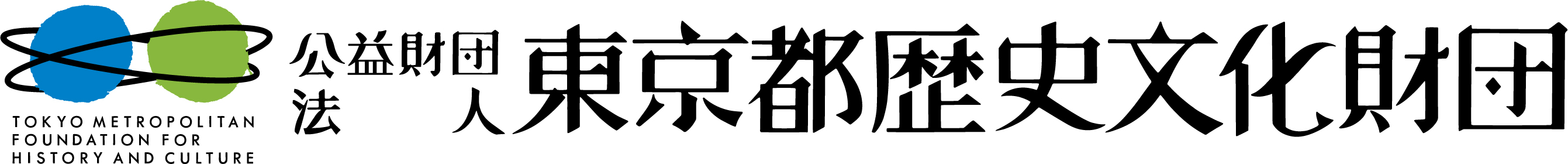アクセシビリティ向上やプログラム開発、ネットワーク構築のため、「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」というプロジェクトを推進するアーツカウンシル東京。社会共生担当として働く大高有紀子さんとチームリーダーの駒井由理子さんは、各施設と東京都の取りまとめや調整を担います。それぞれの仕事内容や入団の経緯についてうかがいました。
※部署名と肩書は取材当時のもの
(中編はこちら)

アクセシビリティがインフラになることをめざして。大高有紀子さん

2024年4月からアーツカウンシル東京で社会共生担当として勤務する大高有紀子さん。前職では別の分野で仕事をしていたため美術館や博物館は利用する側でした。文化施設が好きだけれど、ろう者として情報保障がない状況にもどかしさも感じていました。ですが、あるとき手話通訳付きのアーティストトークに参加した経験が、いまの仕事につながるきっかけになったそうです。
「それまでは作品をただ見るだけ。イベントに参加したいと思っていても、情報保障がついていなかったり、あったとしても『専門知識が必要だろう』と思い、ハードルが高かったのです。ですがアーティストにはじめて直接会って、その制作意図やアーティストの想いを手話通訳を通して対話すること、知ることができた経験は大きな感動でした。この経験をぜひ多くの人に感じてもらいたい、いまの状態ではもったいない、と思うようになりました」

現在はおもに2つの業務を担当しています。1つは各施設のアクセシビリティの状況をまとめる仕事。もう1つは手話通訳者に向けた研修の運営担当です。一口に「手話通訳」といっても、専門分野や得意分野はさまざま。教育現場や行政、自治体現場に比べると、芸術文化分野に特化した手話通訳者はまだ多くはありません。そのためアーツカウンシル東京では今年度、芸術文化分野の手話通訳研修を開催しました。

この仕事を始めて半年ですが、うれしかったのは手話通訳付きのイベントに参加したろう者からの声でした。
「別の展示を見にきていたけれど、たまたまやっていたこのイベントに参加できて喜んでいた」という声をある館からきいたんです。そのイベントは事前申込制ではなく当日参加できるイベントでした。
情報保障付きイベントの現状として、日時が限られておりかつ事前申し込み制や定員を設けているケースが多いです。施設の展示を見に行く際に、興味ある関連イベントやほかの展示関連イベントがたまたま当日開催されていたとしても、情報保障がついていないケースがあります。つまり、情報保障がある日時を調べてからでないと参加することができないという状況になっているのです。当日参加できるイベントの場合、運営側としては情報保障などアクセシビリティを必要としている参加者が来るかどうか事前に分からないのですが、利用者にとってはふらっと立ち寄って参加することができたという状況が生まれていました」
前編の座談会では「アクセシビリティが『インフラ』のようになってほしい」と話していた大高さん。「今後も、たとえば私のように当事者が、芸術文化施設等の運営側にもっと入ることで、環境を改善できる機会が増えるといいなと思っています」と語ります。
文化施設の未来への架け橋となるように。駒井由理子さん

事業調整担当課長として、社会共生チームを率いる駒井由理子さんは、前職は神奈川県にあるホール・劇場を管理する団体に勤めていました。いまの仕事につながるきっかけは約10年前。ホールの貸出業務を担当していたころです。
「ホールの管理は大好きな仕事でした。ピアノ教室の発表会やカラオケ大会だったり、イタリアの歌劇場のオペラだったり、ホールにお客さまが来て笑顔で帰っていく姿を見てシャッターをおろす。それが楽しかったんです」
あるとき偶然にも、ディスレクシア(*)や肢体不自由などさまざまな障害者団体から大会の申し込みが集中した時期がありました。ただ、そのホールは築年数を経た建築のため「バリアだらけ」だったといいます。
「どうやったら安心して来ていただくことができるか。大きな大会のため、申し込みから本番までは2年ほど時間があったので、猛勉強をしました」
イベントは無事に成功。ただこの経験で得た知識をもっと周囲の職員にも広めたい、と定期的に講師を呼んで講座をひらくなど地道に活動を続けていきました。やがて所属する財団に、文化施設の立場から共生社会を考えていく部門ができ、チームをまとめるリーダーとなりました。
*学習障害のひとつとされ、理解能力に異常がないが、文字の読み書き学習には困難を抱える障害

現在はアーツカウンシル東京の事業調整担当課長として各施設の社会共生担当を取りまとめる役割を担っています。「取りまとめ」とは、都のプロジェクトを各施設の特徴に合わせてどのように実現していくかを考え、伝える仕事です。
東京都とアーツカウンシル東京と都立文化施設では「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキュー」というプロジェクトのもと、2023年度は文化施設に行くまでの「情報サポート」、2024年度は実際に芸術を楽しむための「鑑賞サポート」、2025年度は企画や運営に参加するための「参画サポート」という3段階で計画を推進しています。

クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーwebサイト内「アクセシビリティに関わる取組一覧」では、高齢者、障害者、乳幼児、海外にルーツをもつ人などを対象とした取組や情報保障支援等のあるプログラム、芸術文化の鑑賞や体験をサポートするツールなど多角的に紹介しています
この仕事は「マイナスをゼロにする」役割だと、前編の座談会でも話していた駒井さん。いまは「文化施設が一つの役割を終える転換期でもある」と指摘します。
「高度経済成長により公共施設が集中的に開館・整備されてきた時期から50〜60年ほど経ち、耐用年数という物理的にも役割が終わる時期です。そういう意味でも文化施設のあり方を捉えなおす時期なのかもしれません。そこから次に芸術文化を楽しむ段階に行くための架け橋が、アクセシビリティの整備なのではないかと思っています」
いろいろな人が隣り合って一つの芸術作品を楽しむことができる次の未来をめざし、社会共生担当としてその一歩を踏み出しています。
取材・文:佐藤恵美 撮影:栗原論 手話通訳:飯泉菜穂子、戸井有希
クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー
乳幼児から高齢者まで、障害のある人もない人も、そして海外にルーツをもつ人たちも、だれもが文化施設やアートプログラムと出会い、参加しやすいように文化芸術へのアクセシビリティ向上に取り組むプロジェクト。国内外の文化施設、地域の課題に関わるNPOなどとも連携し、それぞれの視点や経験をいかしながら、これからの文化芸術活動に必要な取組を推進していきます。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
https://creativewell.rekibun.or.jp/about/